ネットショップ・オンラインショップの開業は誰でも可能ですが、成功には正しい手順が必要といえます。
この記事は、ネットショップ業界で10年以上のサービス提供実績を持つ STORES のネットショップ が、初心者から上級者まで、成功の極意をすべて網羅した「ネットショップ開設の完全ガイド」です。
販売商品やコンセプトの決定から、自社サイト(ASP型)かECモール(モール型)かの選び方、必要な申請・届出、サイト制作、集客・運用開始までの全手順を解説いたします。ぜひ参考にしてみてください。
ネットショップの種類は主に3つ
ネットショップの作成方法は、「モール型」「ASP(アプリケーションサービスプロバイダ)型」「ソフトウェアインストール型」の3つに大きく分けられます。それぞれ、コストや自由度、難易度が異なります。
ASP型
ASP型は、クラウド上で提供されるシステムをレンタルし、短期間・低コストでショップを開設できる形式です。
専門知識が不要で、サーバーの運用保守やセキュリティ対策をサービス提供元が行うのが最大のメリットです。しかし、デザインや機能のカスタマイズ性が低く、決められたテンプレートや機能に制約がある点がデメリットです。まず手軽にECを始めたい初心者や、低コストで運営したい事業者に適しています。
例として、STORES ネットショップ やShopifyがあります。
モール型
モール型は、Amazonや楽天市場などの巨大なショッピングモール内に自店舗を出店する形式です。
最大のメリットは、モール自体の圧倒的な集客力を利用できるため、自社の知名度が低くても集客に困りにくい点です。一方、デメリットは、デザインや機能のカスタマイズ性が低く、モール内で競合との価格競争に陥りやすいこと、また売上に応じた手数料が高くなる傾向があることです。EC初心者や集客に不安がある事業者に適しています。
例として、楽天市場やAmazonがあります。
ソフトウェアインストール型
ソフトウェアインストール型は、自社でサーバーを用意し、ECサイトのソフトウェアをインストールして構築する形式です。
最大のメリットは、システムやデザインのカスタマイズ自由度が最も高く、自社のブランドを完全に表現できる点です。また、長期的なランニングコストを抑えやすい傾向もあります。しかし、デメリットとして、サーバー準備やセキュリティ対策、運用保守に専門的なIT知識と高い初期コストが必要です。大規模なEC展開を目指す企業や、システムを完全に内製化したい事業者に適しています。
例として、EC-CUBEなどのオープンソースソフトウェアがあります。
ネットショップを開業するための基礎知識と流れ
インターネットの普及により、誰でも気軽に自分のお店を持てる時代になりました。しかし、成功するためには、いくつかのポイントを押さえておくことが大切です。
- 販売商品やお店のコンセプトを決める
- 販売する商品は仕入れか作るか
- 販売可能・不可能か確認する
- 必要な申請や届出を確認する
- 自社(カート型)かモール型か選ぶ
- ネットショップのサイト制作
- ネットショップの運用開始
まず、販売する商品やショップのコンセプトを明確にしましょう。開業に向けて「どんなお店にしたいのか」を決めておくと、ターゲットとなるお客さまのニーズに合った店舗づくりがしやすくなります。また、販売する商品が法律や規制に抵触しないかを事前に確認し、必要な許可や届出を済ませておくことも必要です。
次に、ネットショップの運営方法を決めます。自社サイト(カート型ショップ)を作るのか、楽天市場やAmazonなどのモール型ショップに出店するのか、それぞれのメリット・デメリットを理解し、最適な方法を選びましょう。
開業後は、集客や販売促進のための施策を考え、SNSや広告を活用してお店の認知度を高めていきます。ネットショップは開業するだけでなく、運営を続けていかなければなりません。焦らず、一歩ずつ準備を進めていきましょう。
販売商品やお店のコンセプトを決める
.jpg)
ネットショップを成功させるには、まず「何を売るか」「どんなショップにするか」を明確にすることが大切です。目的が曖昧なまま開業するとターゲットが定まらず、集客や販売戦略が難しくなります。
まずは、販売する商品を選びましょう。幅広いジャンルを扱うのか、こだわりの商品に絞るのか、オーダーメイドやハンドメイドなどの受注生産にするのか、それぞれの選択肢で運営の方法が異なります。また、取り扱う商品が法律や規制に抵触しないかも確認が必要です。
STORES ネットショップ なら物販だけでなく、ダウンロードコンテンツや電子チケットの販売もできます。グッズ販売はもちろん、レシピの販売やチケット販売など行うことも可能です。
次に、ネットショップのコンセプトを決めます。たとえば「ナチュラル志向の雑貨店」「国内産食材にこだわった食品販売」など、明確なテーマを持つことで、お客さまにとって魅力的なショップになります。コンセプトにより、自社サイトで世界観を作り込むか、大手モールで広く販売するかなど、ネットショップの運営方法が変わってくるでしょう。
販売商品とコンセプトを決めることでブランドの方向性が明確になり、ネットショップ運営がスムーズに進みます。開業前にしっかりと計画を立て、独自の魅力を持つネットショップを目指しましょう。
販売する商品は仕入れか作るか
仕入れ商品を販売する場合、メーカーや卸業者から商品を購入し、ネットショップで販売します。人気のある商品を扱うことで売上の予測が立てやすく、比較的スムーズに運営できるのがメリットです。
また、在庫管理や発送を代行してくれるサービスを利用すれば、運営の負担を軽減することもできます。しかし、仕入れにはコストがかかるため、適切な価格設定が求められます。
一方で、オリジナル商品を販売する場合、自分のアイデアを活かし、唯一無二のショップを作ることが可能です。ハンドメイド品やオリジナルデザインの商品を販売すれば、ブランドの世界観を作り込みやすく、独自性を持ったネットショップにできます。また、中間業者を挟まないため利益率が高くなる傾向があります。
ただし、認知度を上げるためにはマーケティングやブランディングが必要です。とくに開店初期の集客には、時間を要することもあります。
どちらの方法を選ぶかによって運営の方向性が変わるため、自分が扱いたい商品や販売スタイルを考えながら決めることが大切です。それぞれのメリット・デメリットを理解し、理想のショップ運営を目指しましょう。
販売可能・不可能か確認する
ネットショップを開業する際には、販売したい商品が法律上問題なく取り扱えるかを事前に確認することが重要です。特定の商品は、販売に許可や届出が必要な場合があり、それを知らずに販売を始めると後から行政機関から指摘を受けることもあります。
たとえば、酒類・中古品・医薬品・化粧品などは、販売に関する規制が設けられています。これらの商品を扱う場合は、事前に必要な許可を取得し、販売ルールを遵守しなければなりません。また、ネットショップのプラットフォームによっては、独自の規約で販売が禁止されている商品もあるため、利用するサービスの規約も確認しておきましょう。
さらに、都道府県や市町村によって独自の規制がある場合もあります。販売を開始する前に、専門家に相談するなどして準備をすることが大切です。安心してネットショップを運営するために、販売可能な商品かどうかをしっかり確認しましょう。
必要な申請や届出を確認する
ネットショップで取り扱う商品によって、必要な申請や届出が異なります。手続きを怠ると販売ができなくなる可能性があるため、事前に確認しておきましょう。
たとえば、食品を販売する場合「食品衛生責任者」の資格や「食品衛生法に基づく営業許可」が必要です。そのほか、中古品を扱う場合は「古物商許可」、酒類を販売する場合は「通信販売酒類小売業免許」などが求められます。化粧品や医薬品を販売する場合もそれぞれ製造販売許可が必要となるため、事前に管轄の保健所や行政機関に確認しましょう。
また、個人事業主としてネットショップを運営する場合は、税務署に「開業届」を提出することが推奨されます。開業届を提出すると青色申告が可能になり、節税のメリットを受けられる場合があります。
自社(カート型)かモール型か選ぶ
ネットショップを開業する際、運営方法として「自社サイトを構築する」か「ECモールに出店する」かを選ぶ必要があります。ブランドの成長を重視するなら自社サイト、短期的に売上を伸ばしたいならECモールが向いているでしょう。
自社サイトの特徴は、ブランドの世界観を自由に作り込めることです。デザインや機能をカスタマイズできます。ただし、集客施策は自力でおこなう必要があり、SEO・SNS運用・広告などのマーケティング戦略が欠かせません。
一方、ECモールはすでに多くのユーザーが利用しているため、集客しやすい点が最大のメリットです。楽天市場やAmazonなどのECモールは販売手数料がかかるものの、ECモールがおこなうセールやキャンペーンを活用でき、短期間で売上を伸ばすチャンスがあります。
ただし、ECモール独自の規約に従う必要があり、店舗のデザインや運営の自由度が制限されることもあります。
ネットショップのサイト制作
ネットショップのサイト制作は、出店先によって進め方が異なります。自社サイトを構築する場合はネットショップのプラットフォームを選び、デザインや機能の設定が必要です。ECモールに出店する場合は、モールのフォーマットに沿ってショップページを作成し、商品の登録や決済方法の設定をおこないます。
自社サイトでは、ASP型のネットショップ開設サービスを利用すれば比較的かんたんにサイトを作成できますが、カスタマイズ性は、オープンソースやパッケージ型に比べると低めです。オープンソースやパッケージ型のシステムを導入すると自由度は高くなりますが、専門的な知識が必要となります。
一方、ECモールはテンプレートを活用してショップページを作成します。デザインの自由度は低めですが、スムーズに販売を開始できる点がメリットです。
ネットショップでの決済・配送方法を決める
ネットショップにおける決済方法は、顧客が購入を決定する最終段階で、カゴ落ちを防ぎ売上を最大化するために極めて重要です。
総務省の統計※からも、消費者はクレジットカード決済をはじめとする多様な決済手段の利便性を重視していることがわかります。希望の決済手段がない場合、購入を断念する可能性が高まるため、主要な決済方法(クレジットカード払い、銀行振込、コンビニ決済、後払いなど)を幅広く提供し、顧客の利便性と信頼を得ることが成功の鍵です。
一方、配送方法と料金については、ヤマト運輸や日本郵便など、配送業者が定める送料やサービス内容(サイズ・重量・配送スピード)を比較検討し、その費用を基に決定することが一般的です。適切な決済・配送設定は、顧客満足度と業務効率の向上に不可欠といえます。
※参考資料:総務省 情報流通行政局「令和5年通信利用動向調査報告書(世帯編)」(2025年11月)
ネットショップの運用開始
ネットショップを継続的に運営し、売上を伸ばしていくためには、戦略的な運用が欠かせません。
開業してから考え始めるのではなく、開業前の準備段階で受注管理や在庫管理の仕組みを整え、スムーズに運営できる体制を作っておくことが大切です。決済方法や配送業者の選定も、開業前にしっかりと決めておきましょう。
運用を開始したら、集客や販売促進に取り組みます。SEO対策やSNS運用、広告などを活用し、ショップの認知度を高める施策が有効です。たとえば、SNSを活用して情報発信することで、商品やブランドに興味を持ってもらいやすくなります。また、クーポンやキャンペーンを活用し、購入を促す工夫も必要です。
STORES ネットショップ ならば、Instagramとの販売連携もできるので、効率的な集客を実現できます。
販売後の顧客対応も、ショップの成長にかかわる重要なポイントです。スピーディな発送やていねいな対応を心がけることで顧客満足度を高め、リピーターの増加が期待できます。メルマガ配信や特典の付与などをおこない、長期的な関係を築く施策も検討しましょう。
個人ネットショップ開業時に必要な手続き
個人事業主・開業届を提出する
ネットショップを開業する際、まず税務署へ「開業届」を提出することが推奨されます。開業届は、個人事業主として正式に事業を開始したことを届け出るための書類です。提出しない場合の罰則はありませんが、事業を営んでいる証明となるものなので、開業後1カ月以内に提出しましょう。
開業届の提出方法は、税務署へ直接持参するほか、郵送や電子申告も可能です。また、屋号を設定する場合は、商標登録の可否も考慮しながら決めるとよいでしょう。
参考:国税庁「個人で事業を始めたとき/法人を設立したとき」(2025年6月)
確定申告の届出を提出する
ネットショップを運営する個人事業主は、毎年の確定申告が必要です。確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があり、青色申告を選択すると最大65万円の控除を受けられるなど、節税のメリットがあります。
ただし、青色申告を適用するには、事前に「青色申告承認申請書」を税務署へ提出しなければなりません。
青色申告には、10万円控除・55万円控除・65万円控除の3種類があり、それぞれ帳簿の作成方法や必要な書類が異なります。とくに65万円控除を受ける場合は、複式簿記による記帳が求められるため、会計ソフトの導入などの準備が必要です。
確定申告の届出を適切におこない、税務面でのメリットを活かしながらネットショップを運営していきましょう。
参考:国税庁「A1-8 所得税の青色申告承認申請手続」(2025年6月)
ネットショップ開業にかかる費用
ネットショップを始める際には、さまざまな費用が発生します。サイトの開設やシステムの利用料、商品仕入れや撮影機材など、準備するものによって費用は異なります。できるだけ初期費用を抑える工夫をしながら、長期的な運営を考えた予算を立てていきましょう。
出店・サービス・設備などの費用
ネットショップの開業にかかる主な費用には、出店費用・運営サービスの利用料・設備の準備費などがあります。これらの費用は、開業方法や販売規模によって異なるため、事前に計画を立てておくことが大切です。
ネットショップを構築する場合、ASP型サービスを利用すれば無料から始めることも可能ですが、デザインの自由度は限られます。カスタマイズ性の高いサイトを作る場合は、制作費がかかるため、予算を考えながら選びましょう。
加えて、集客のための広告やプロモーションにかかる費用も計算しておくと安心です。
商品の仕入れや製造のための費用
ネットショップで販売する商品の仕入れや製造の費用も必要です。仕入れをする場合、商品代金に加えて送料や手数料が発生することがあるため、事前に費用を確認しておきましょう。
オリジナル商品を製造する場合、原材料費や加工費、パッケージ制作費がかかります。商品を一括で大量発注する場合はコストを抑えられることもありますが、初期の在庫管理には注意が必要です。
また、助成金や補助金、クラウドファンディングなどを活用すれば、初期費用の負担を軽減できる可能性もあります。
ネットショップ開設におすすめのサービス
ネットショップ関連の代行サービスは多数存在するため、どの代行サービスを利用してよいか迷ってしまっている方は多いのではないでしょうか。ここでは、STORES ネットショップ がおすすめするネットショップ関連の代行サービスをご紹介していきます。
おすすめのネットショップ開設サービスについては、こちらでもご紹介しておりますので、ぜひ参考にしてください。
①STORES ネットショップ
②BASE
③メルカリShops
④Amazon
⑤MakeShop
ネットショップを成功させるポイント5つ
ネットショップを軌道に乗せるためには、コスト管理と運営戦略が大切です。思わぬ失敗を防ぐため、以下に紹介する5つのポイントを押さえておきましょう。
①月々かかる固定費を抑える
ネットショップで利益を確保するためには、毎月発生する固定費の管理を徹底することが大切です。
固定費には、ネットショップ開設サービスの利用料・決済手数料・倉庫の賃料・梱包資材代・広告費などがあります。とくに、カートシステムの月額利用料は、売上が安定するまでの負担になりやすいため、無料のネットショップ開設サービスを活用するのもひとつの方法です。
例えば弊社が提供する STORES ネットショップ であれば、無料で使えるフリープラン(月額0円、決済手数料5.5%〜)あるのでネットショップを開業しやすくなっています。
また、事務所や倉庫の賃料を抑えるため、自宅で運営を始めるのも有効な選択肢でしょう。広告費についても、はじめはSNSやSEOを活用した無料の集客方法を試し、売上が伸びてから有料広告を導入することで、無駄な支出を防げます。
くなっています固定費を抑えて利益率を高め、安定した運営を目指しましょう。
②在庫管理を徹底する
ネットショップ運営では在庫管理が極めて重要です。
在庫過多は保管スペースの圧迫や管理の複雑化、売れ残りによる損失リスクを高めます。特に流行商品は需要変動が激しく、季節商品などは売れ残ると値下げ販売のリスクを負います。安定した収益確保のため、最初は少量仕入れから始め、販売データに基づき適切な在庫量を調整することが大切です。
もし実店舗もすでにあるのならば、 STORES レジ を利用し、実店舗とネットショップの在庫を一元管理することもできます。
在庫管理については、こちらの記事でもご紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。
③集客は無料のものから
ネットショップを開業したばかりの段階では、広告費をかけずに集客する方法を活用するのが賢明です。SEO対策やSNS運用など、無料でできる施策を積極的に取り入れ、コストを抑えながら認知度を高めていきましょう。
たとえば、XやInstagramを活用して商品情報を投稿したり、ブログで役立つコンテンツを発信すると、自然な形でユーザーの関心を集められます。また、検索エンジンで上位表示されるようにサイトの構造を整えることで、広告費をかけずにアクセスを増やすことも可能です。
最初から有料広告に頼るのではなく、無料の集客方法を活用しながら、売上が安定してきた段階で広告投資を検討するのが理想的です。
④顧客に信頼や満足感を与える
ネットショップでは、梱包の丁寧さ、迅速な発送、誠実な問い合わせ対応が顧客満足度を高め、リピーターを生みます。
リピーター獲得のための戦略として、こうした基本対応の徹底に加え、購入直後のお礼状や次回割引クーポンを同梱したり、DM(ダイレクトメール)を配信したりすることが効果的です。
さらに、レビュー投稿へのインセンティブを提供し、顧客との信頼関係を大切に築くことが、長く愛されるショップの秘訣です。
⑤炎上しないように注意する
ネットショップの運営では、SNSを活用する機会が多くなりますが、発信内容には十分な注意が必要です。過激な表現や誇張しすぎた広告は炎上の原因となり、ブランドの信頼を損なう恐れがあります。
たとえば、誤解を招くようなキャッチコピーや、競合を批判するような発言は避けるべきです。また、顧客対応においても、不適切な対応が拡散されると、ブランドイメージに大きな影響を与えます。
炎上を防ぐためには、慎重な言葉選びと誠実な対応を心がけることが大切です。信頼を積み重ねられるように運営していきましょう。
ネットショップの成功事例を知ろう!STORES ネットショップ の成功事例3選
ネットショップを開設する際には、成功しているネットショップのデザインや取り扱っている商品などを参考にすると非常に勉強になります。ここでは、STORES ネットショップ がご紹介する成功事例を3選お伝えしていきます。
ネットショップのコンセプトを設計する
ネットショップで成功したいと考えるならば、サイトのコンセプトをしっかりと設計することが大切です。コンセプトとは、自分のネットショップがユーザーに提供する価値観・世界観・ベネフィット(利点)を表したものを指します。
コンセプトがしっかりとしているサイトは独自性を持っており、競合のサイトよりも抜きん出た印象をユーザーに残します。その結果、ユーザーの購買意欲が掻き立てられ、数あるネットショップの中から選ばれるようになるのです。
ネットショップの成功事例①:餃子のかわしも

「餃子のかわしも」は、長崎の餃子を専門に取り扱うお店のネットショップです。焼きたての餃子を急速冷凍して梱包し、おいしい餃子を全国に発送しています。
アイキャッチ部分の手書き調のロゴや店名表記により、手作り餃子を日々提供する、人情味のあるあたたかい雰囲気のコンセプトがよく表されています。目を引きやすい位置に期間限定商品のバナーを大きく配置しており、ユーザーの購買意欲を促進するレイアウトになっていることがおわかりいただけるでしょう。
商品紹介では、「定番」「インスタ掲載」「メディア掲載」「NEW」「ギフト」などと端的でわかりやすいメッセージが表示されているため、ユーザーは一目でどんな属性の商品なのかを理解することができます。
また、Instagramの公式アカウントを運用しており、SNSからの集客に成功している点も特筆すべきところだといえるでしょう。
ネットショップの成功事例②:iCONOLOGY
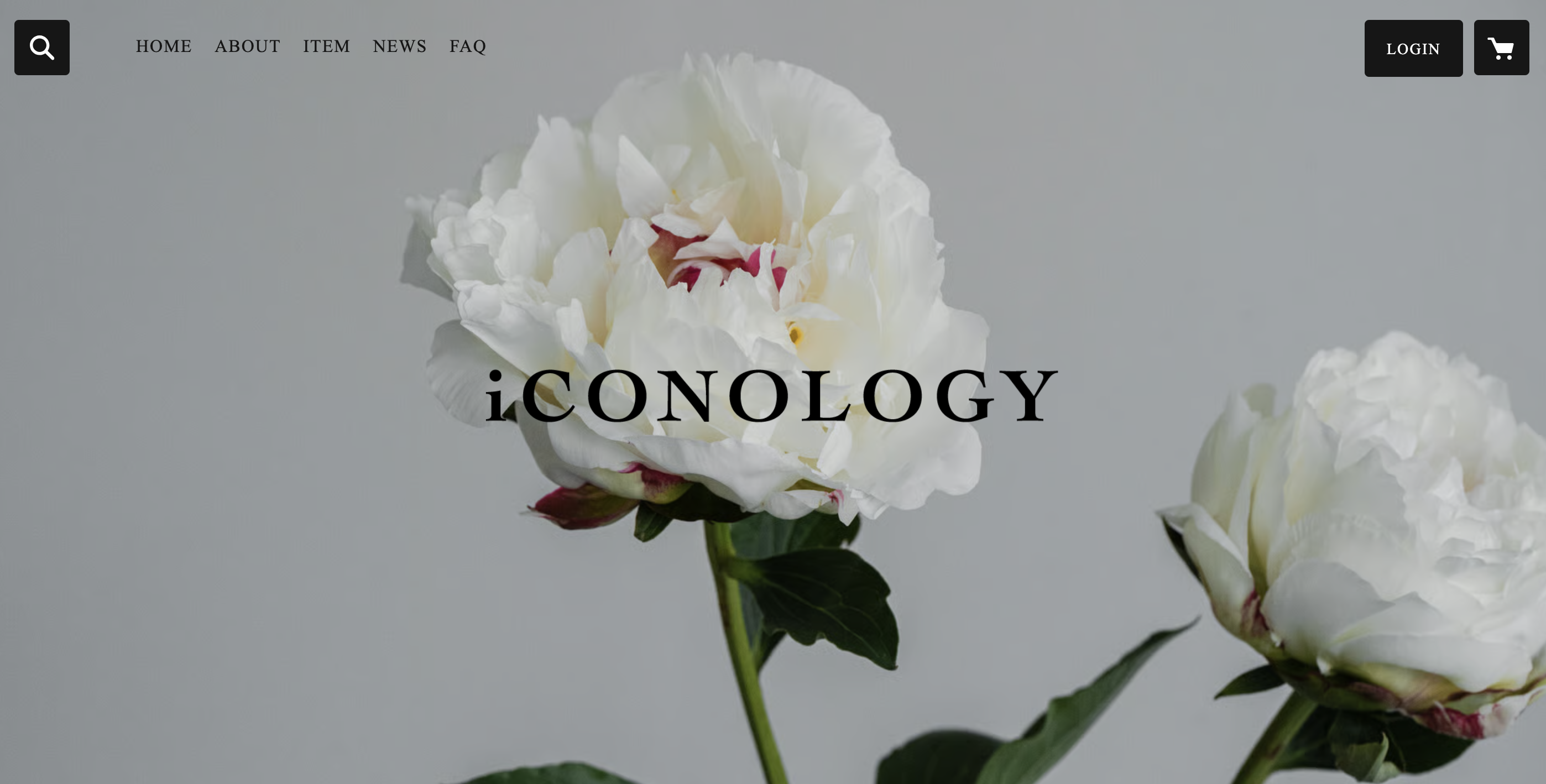
iCONOLOGY(イコノロジー)は、刺繍工房の3代目が手がける、細やかで美しい刺繍を施した洋服を取り扱うアパレルブランドのネットショップです。
アイキャッチ部分に大きなブランドロゴと刺繍を施した洋服やブランドイメージを配置しています。極力無駄な表現を省いたミニマルなサイトデザインが、ブランド自体のコンセプトを際立たせていることがおわかりいただけるでしょう。
商品一覧には「再入荷」「NEW」「SOLD OUT」「予約販売」などの表記がされており、一目でどのようなステータスの商品なのかを理解することができます。なお、「SOLD OUT」のステータスの商品もあえて表示させておくことにより、売り切れが続出している人気ブランドであることをユーザーに伝える意図も感じられます。
まとめ
今回は、ネットショップの開設から運用に至るまで、知っておくべき知識を初心者でもわかりやすいように、あらゆる項目を網羅してご紹介してきました。こちらの記事を読んで、お伝えしてきた施策をしっかりと実践していただければ、売上の上がるネットショップを立ち上げ、ネットショップ運営を成功させることができることでしょう。
ネットショップを開設することは、ネットショップ作成サービスを利用すれば決して難しい取り組みではありません。初心者の方で「ノウハウがないので自分だけではネットショップを立ち上げることはできない」と諦めていた方は、是非とも挑戦してみてください。
ご紹介してきた通り、一人で全ての対応が難しい場合には、制作代行などの利用を検討することで、よりスムーズにネットショップ開設を実施することができます。この記事を読んだことを機会にして、あなただけのネットショップを運営してみてはいかがでしょうか。

キーワード
この記事を共有する

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)